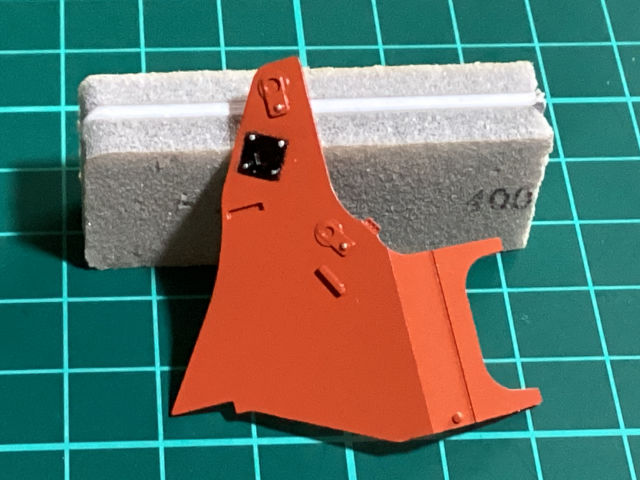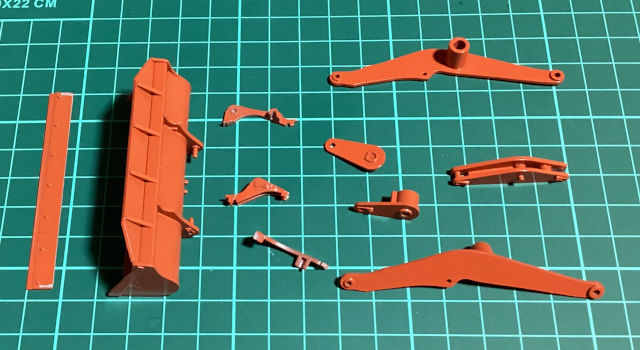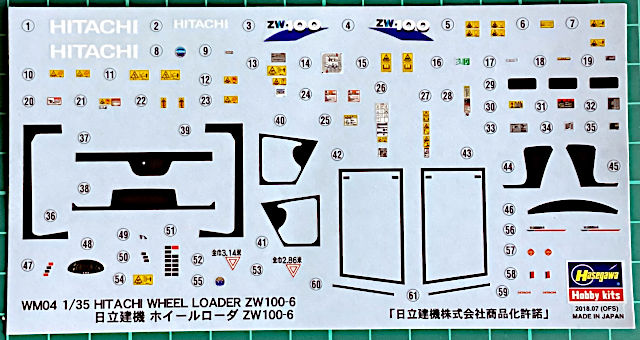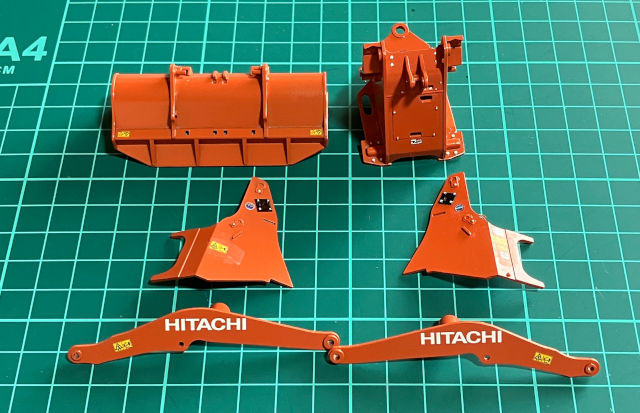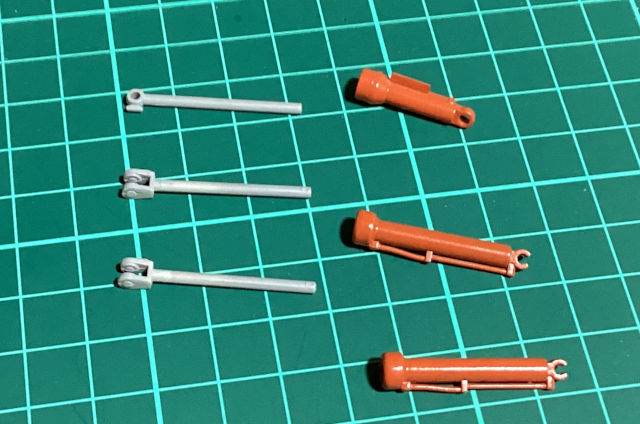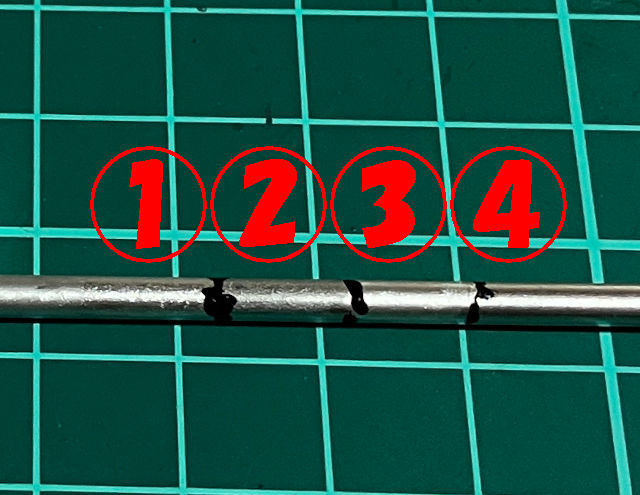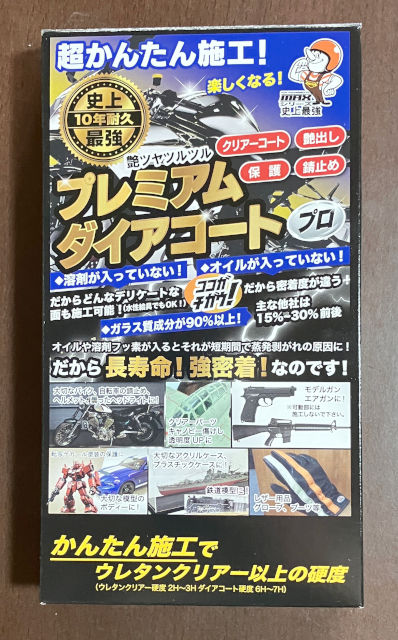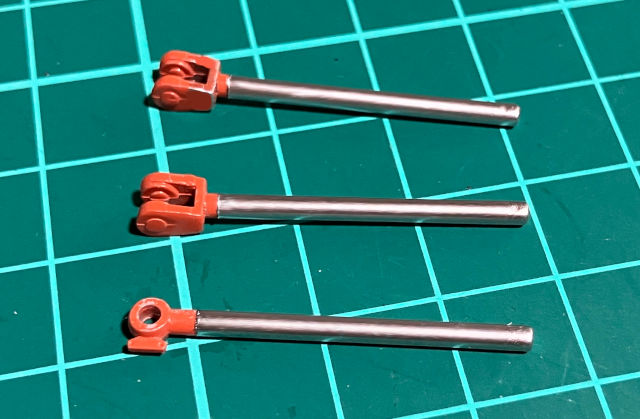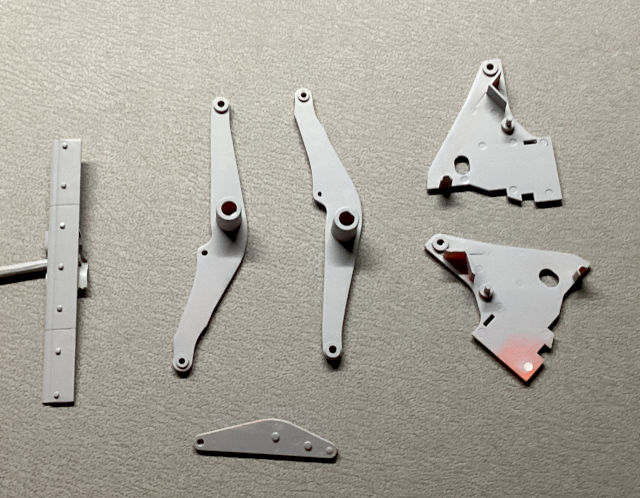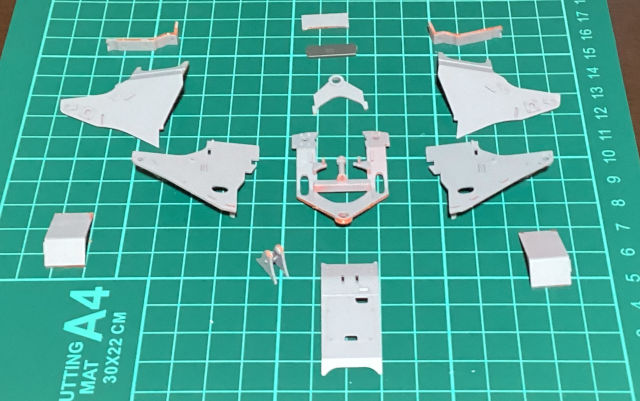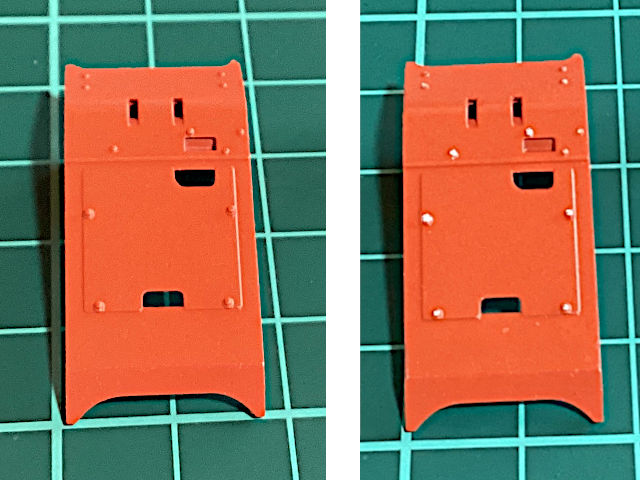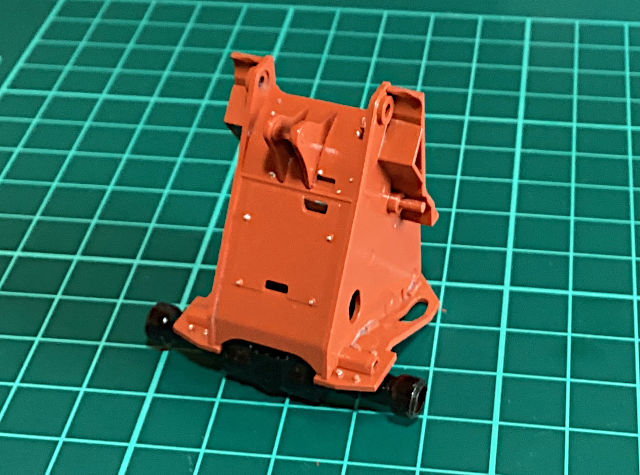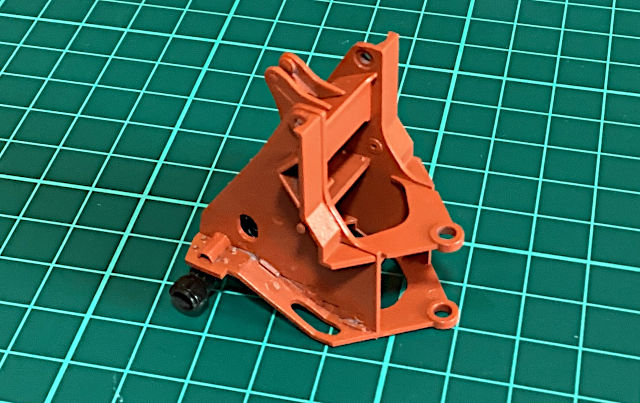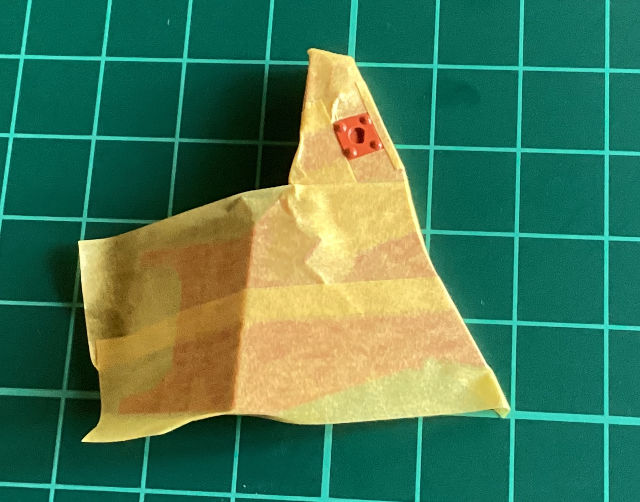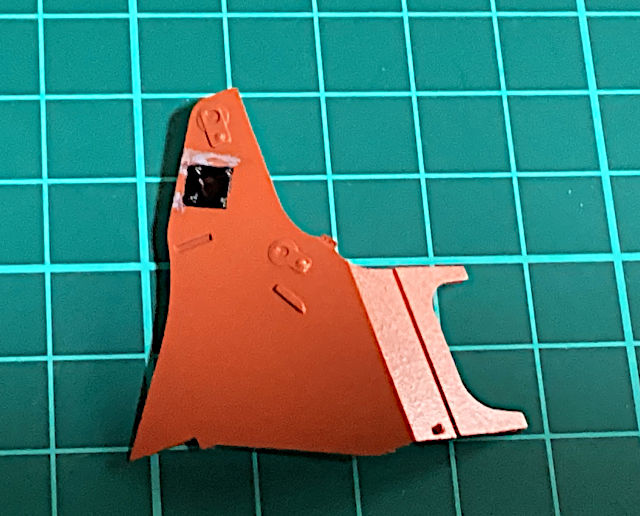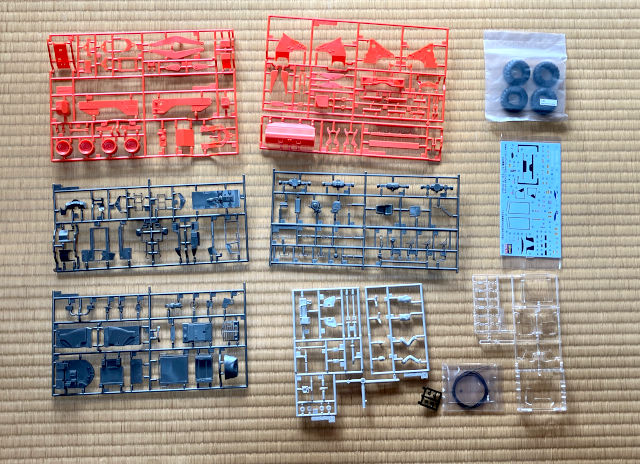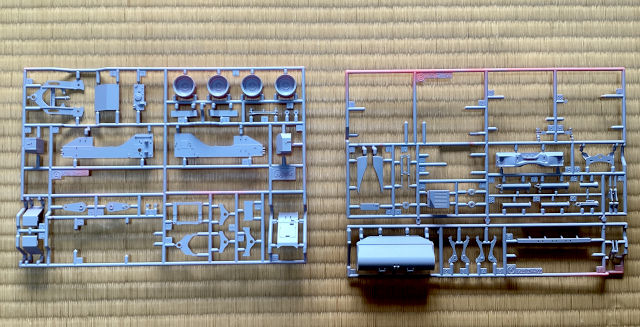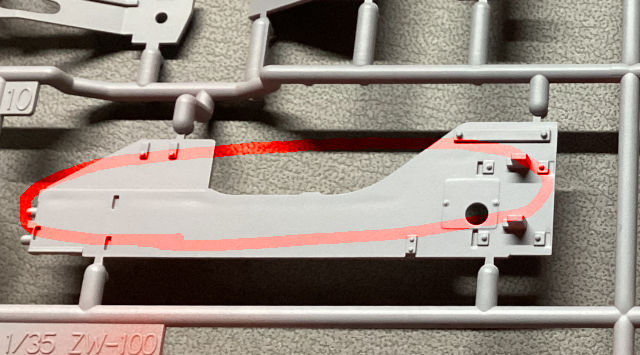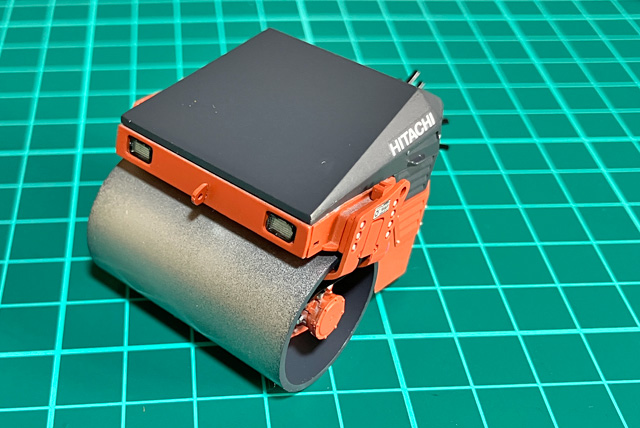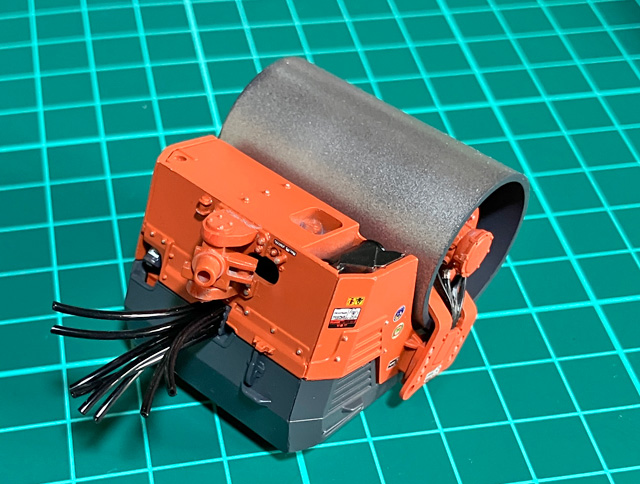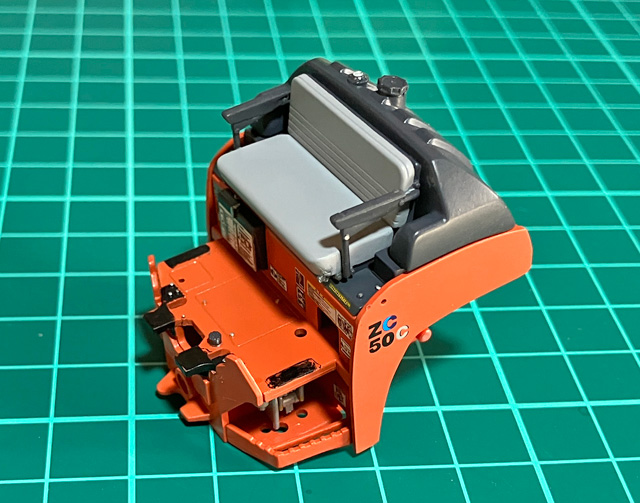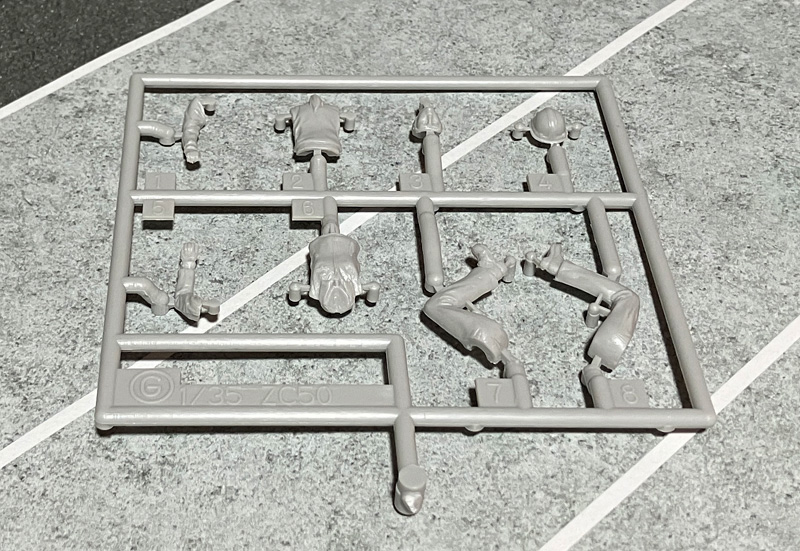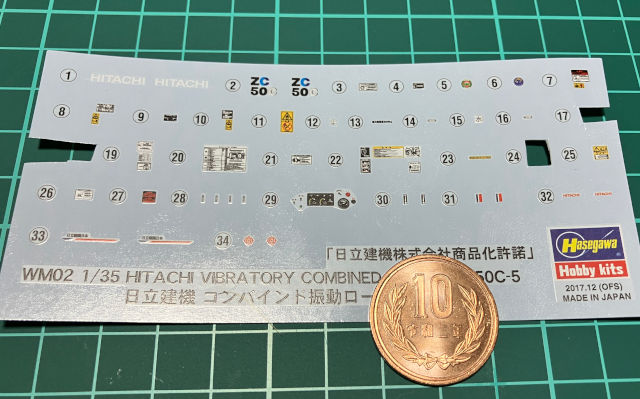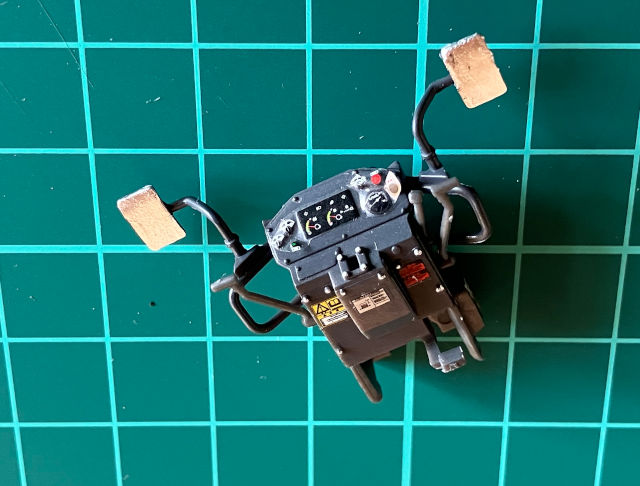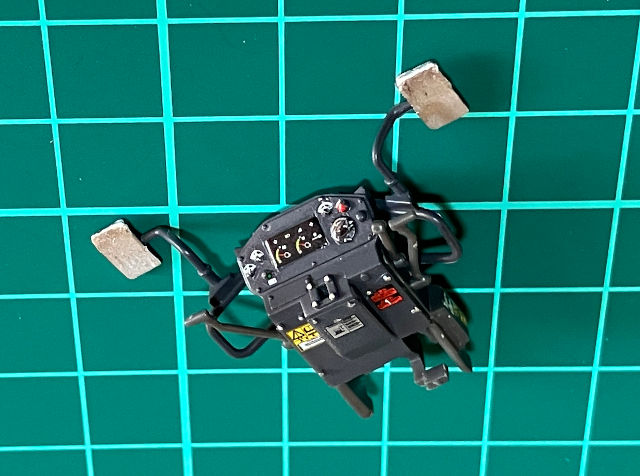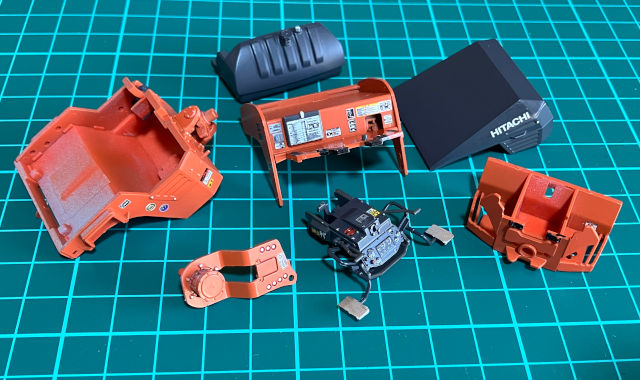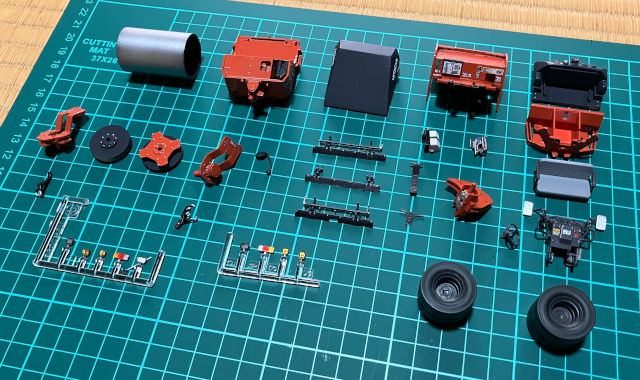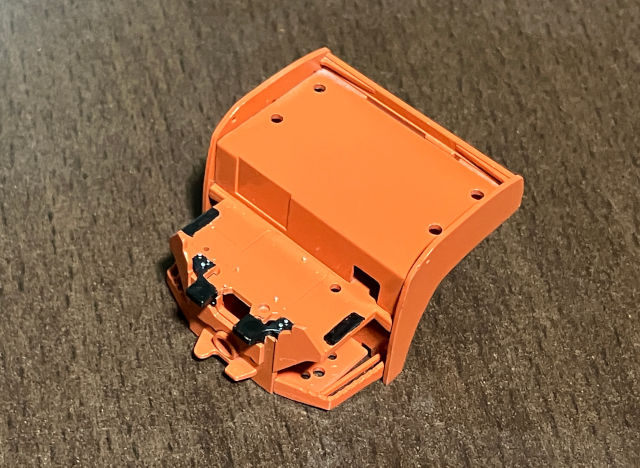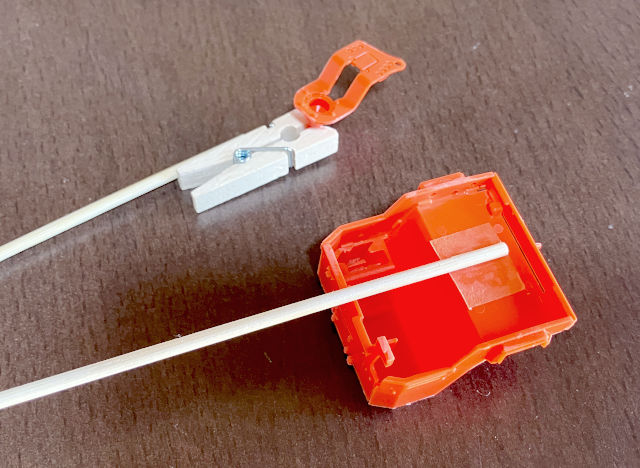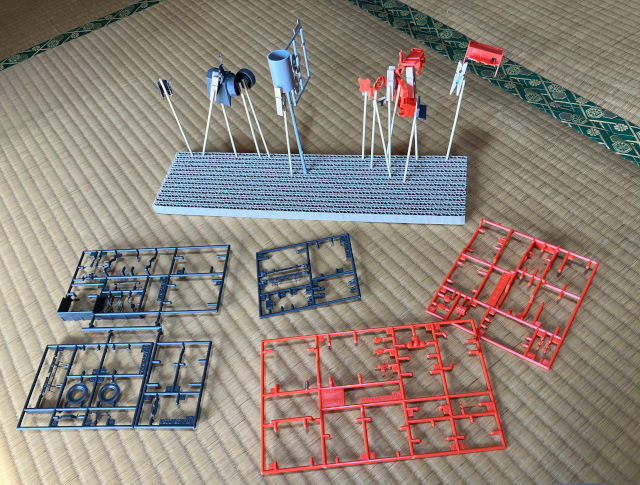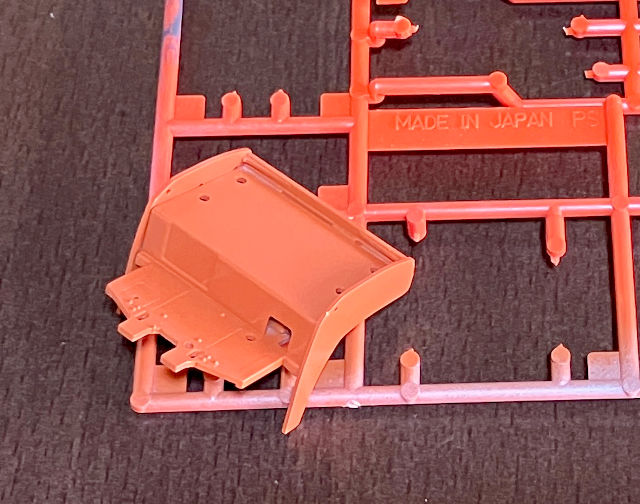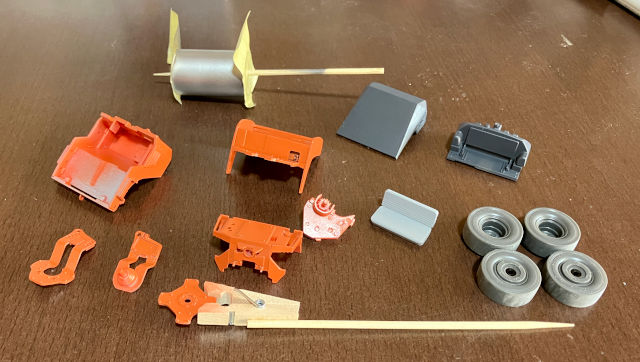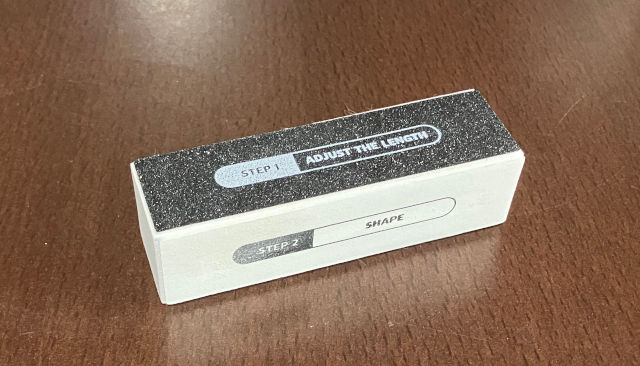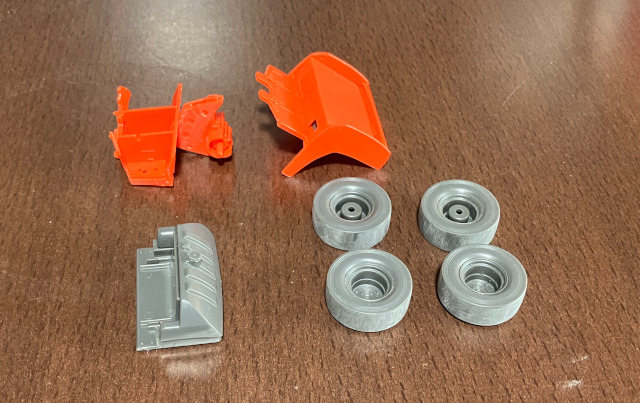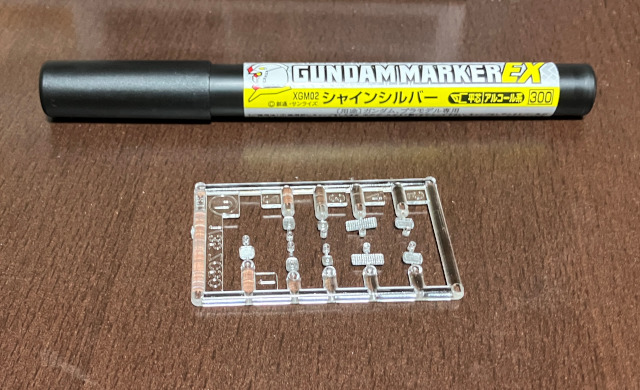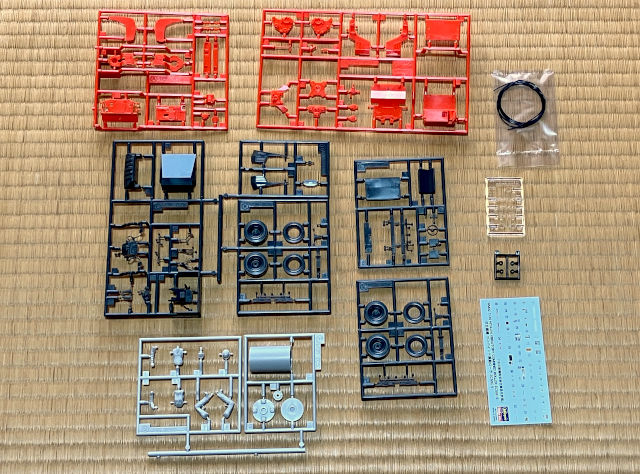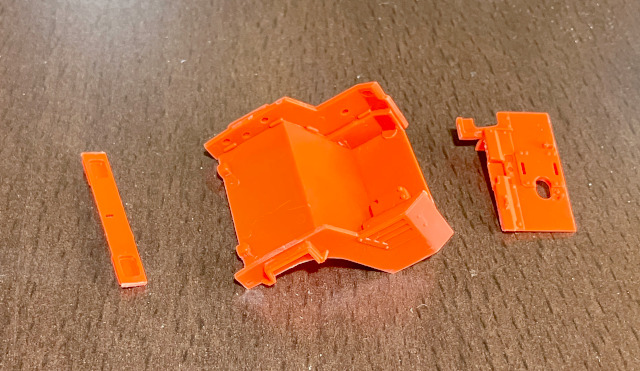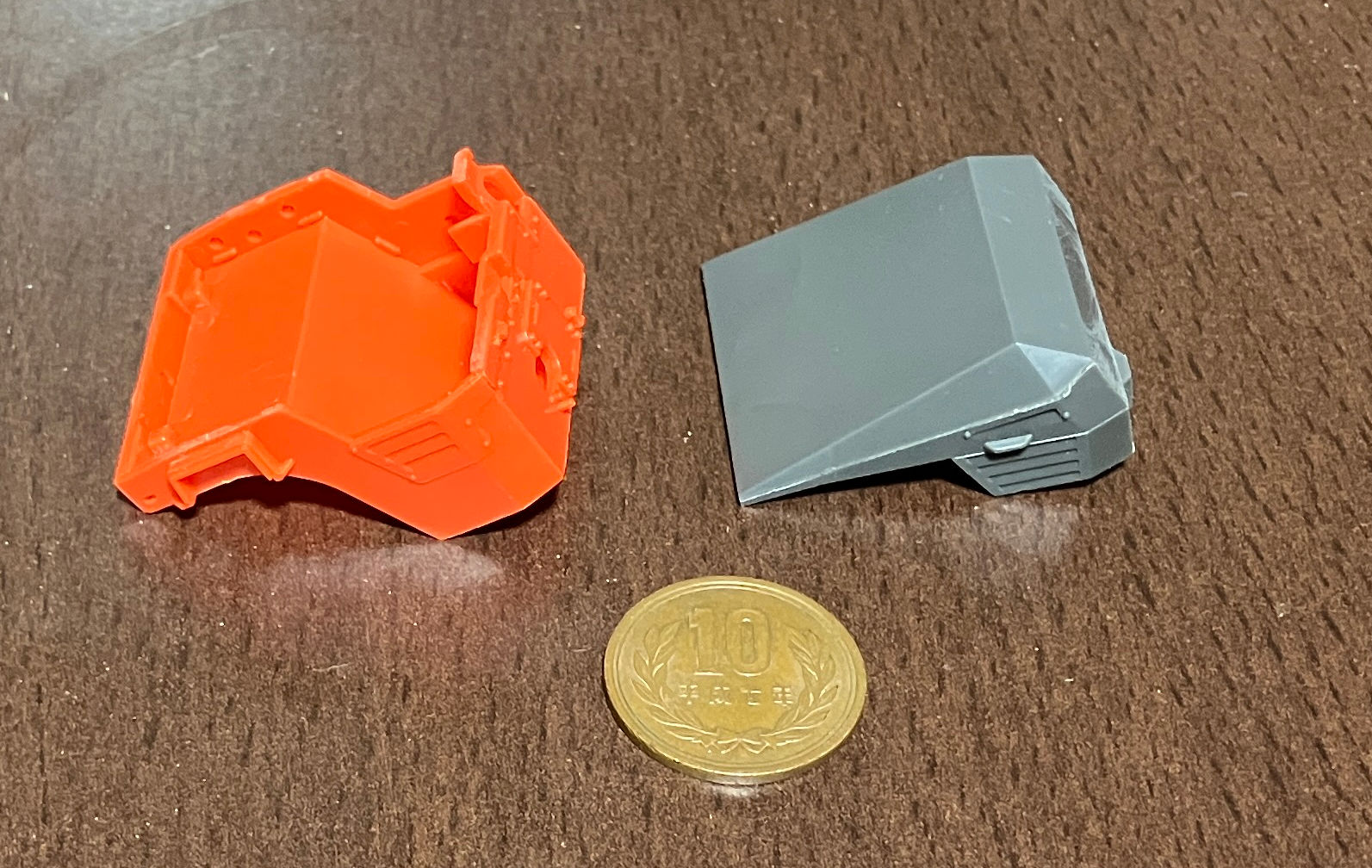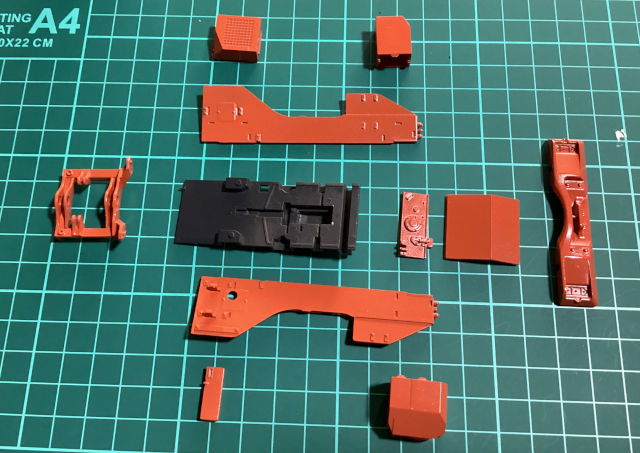 車体の後部フレームを塗装。左端のパーツは前後のフレームをリンクするパーツ。つまりくびれの元ですね。これは7個のパーツを組み合わせるんですが、のりしろというか接着しろが小さく、パーツが取れやすくて難儀しました。力が加わる所なのでガッツリ接着です。
車体の後部フレームを塗装。左端のパーツは前後のフレームをリンクするパーツ。つまりくびれの元ですね。これは7個のパーツを組み合わせるんですが、のりしろというか接着しろが小さく、パーツが取れやすくて難儀しました。力が加わる所なのでガッツリ接着です。
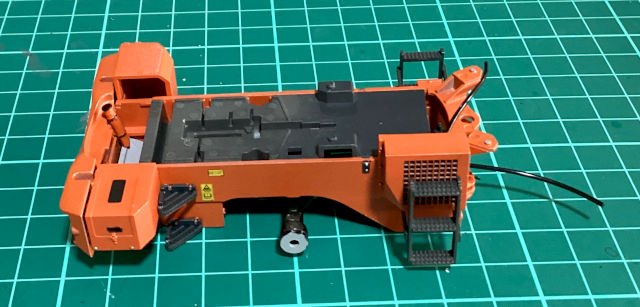 細かい部分を塗り分けて合体。右端に出てるのは動力パイプです。その左の格子状のところは墨入れしました。
細かい部分を塗り分けて合体。右端に出てるのは動力パイプです。その左の格子状のところは墨入れしました。
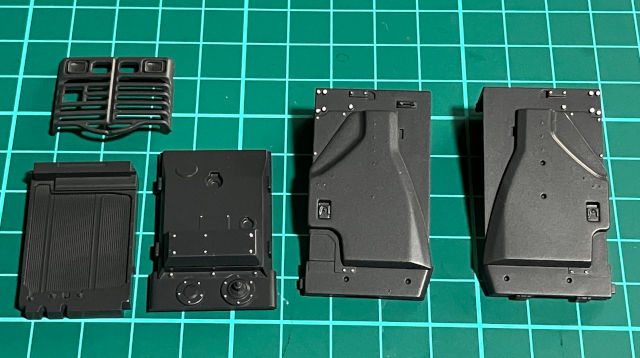 こちらはエンジン。ジャーマングレーに塗ってボルトに銀ポチを。黒に銀は映えますね~。いい感じです。
こちらはエンジン。ジャーマングレーに塗ってボルトに銀ポチを。黒に銀は映えますね~。いい感じです。
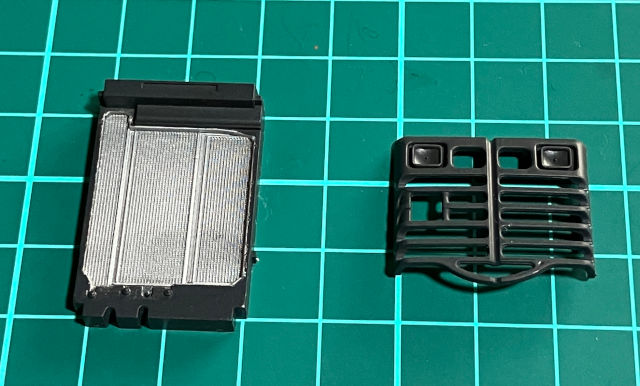 後端にあるラジエターは塗り分けでシルバーをスプレー。なんかシルバーがはみ出してますが、右にあるグリルがかぶさってラジエターは見えにくくなるのでこれでヨシ!
後端にあるラジエターは塗り分けでシルバーをスプレー。なんかシルバーがはみ出してますが、右にあるグリルがかぶさってラジエターは見えにくくなるのでこれでヨシ!
 エンジン組上げ。ほらラジエターあんま見えない。下部分も後部バンパーで隠れます。
エンジン組上げ。ほらラジエターあんま見えない。下部分も後部バンパーで隠れます。
リアライトや黄色い注意書きのデカールも貼って、さらにいい感じ。
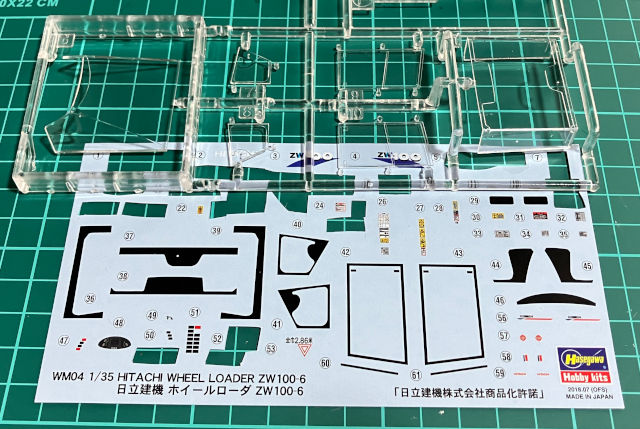 さて、難関であるキャブにいざ着手。その窓枠はフチに黒いデカールを貼るようになってます。事前情報によるとこのデカールが大変なんだとか。あな恐ろしや。
さて、難関であるキャブにいざ着手。その窓枠はフチに黒いデカールを貼るようになってます。事前情報によるとこのデカールが大変なんだとか。あな恐ろしや。
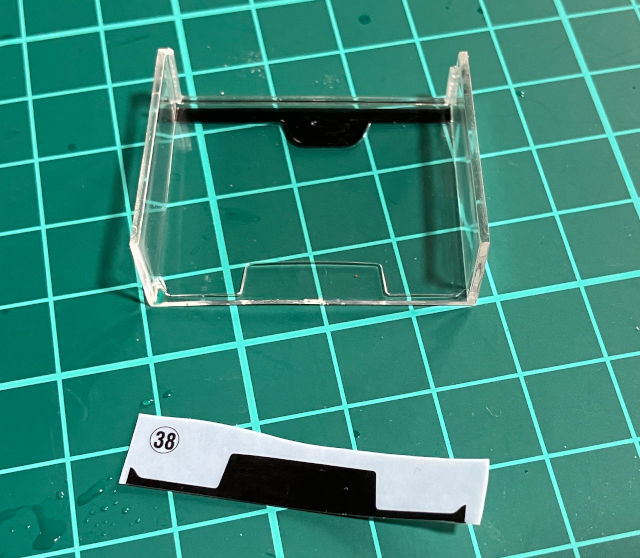 まずはリアウインドウ。うわ、ほんとに大変だ。デカールはパーツの裏側に貼ります。んでパーツにあるデカールと同じ形のモールドは表側にあります。なんでじゃろ。
まずはリアウインドウ。うわ、ほんとに大変だ。デカールはパーツの裏側に貼ります。んでパーツにあるデカールと同じ形のモールドは表側にあります。なんでじゃろ。
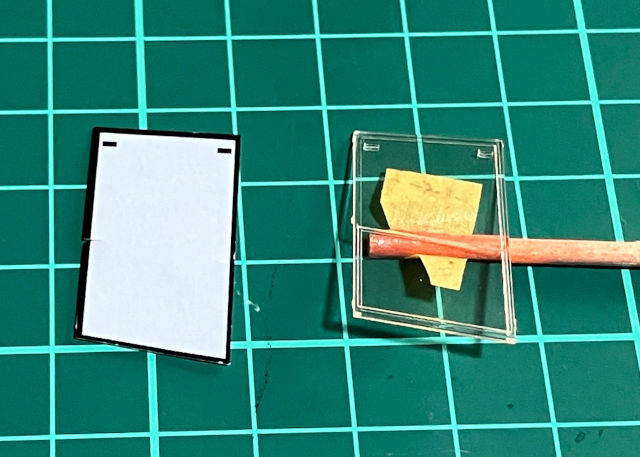 最難関はこのサイドウインドウ。デカールはフチだけあって真ん中は抜けてまして、とってもヨレやすいです。しかもクリアパーツとデカールのサイズが微妙に合ってないです。
最難関はこのサイドウインドウ。デカールはフチだけあって真ん中は抜けてまして、とってもヨレやすいです。しかもクリアパーツとデカールのサイズが微妙に合ってないです。
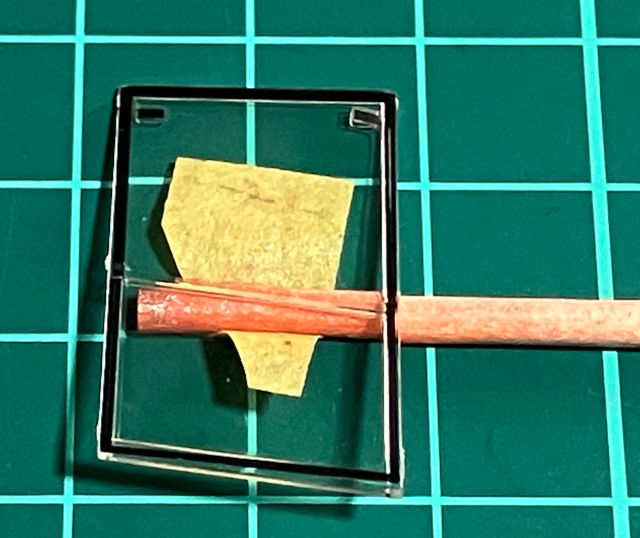 1時間かけて何とか貼りました。でも逆側のサイドウインドウもあるんですわ。大変ですわ。
1時間かけて何とか貼りました。でも逆側のサイドウインドウもあるんですわ。大変ですわ。
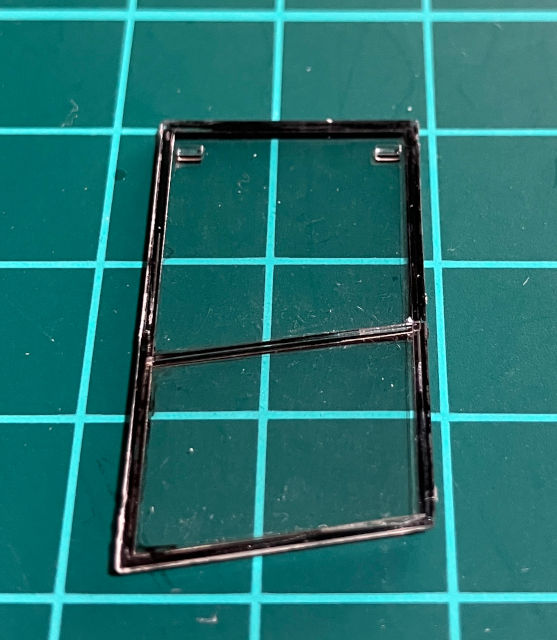 うまくいったと思って表側から見たらこんな感じ。ぐは。デカールがちゃんと密着してないのか、あちこちが白っぽく光っちゃってます。デカールがないパーツの小口も光っちゃってます。
うまくいったと思って表側から見たらこんな感じ。ぐは。デカールがちゃんと密着してないのか、あちこちが白っぽく光っちゃってます。デカールがないパーツの小口も光っちゃってます。
結局このあと塗装で全体をレタッチしました。最初から塗装した方が仕上がりも綺麗で良さそうです。